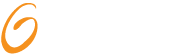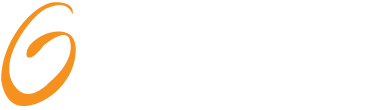不動産のこと個人間売買
費用(報酬)
- 基本報酬
- 最低額200,000円(税抜)
- ※「売買契約書」の作成を含んだ報酬です。
- 登記情報
- 300円/1通
不動産の権利関係を確認。
- 登記簿謄本
- 1,000円/1通
所有権移転の確認。
- 固定資産税評価証明書
戸籍謄本・住民票等 - 1,500円/1通
(ご自身で取得された場合にはかかりません。)
- ※上記費用は税抜です。
費用(実費)
- 登録免許税
- 建物:固定資産税評価額×2%
土地:固定資産税評価額×1.5%
- 登記情報
(登記簿の事前確認) - 不動産の個数×332円
- 登記簿謄本
(登記完了後) - 不動産の個数×480円
- 固定資産税評価証明書
- 概ね300円~350円/1通
- 戸籍謄本・住民票等
- 概ね200円~450円/1通
- ※その他、郵便を利用した場合、郵便代実費をいただきます。
個人間売買とは?
不動産を売買するときは、一般的に下記の図のように、まず仲介の不動産業者と媒介契約をします。次に不動産業者が買主・売主を見つけてきます。そして条件が整えば、買主と売主が不動産の売買契約をします。
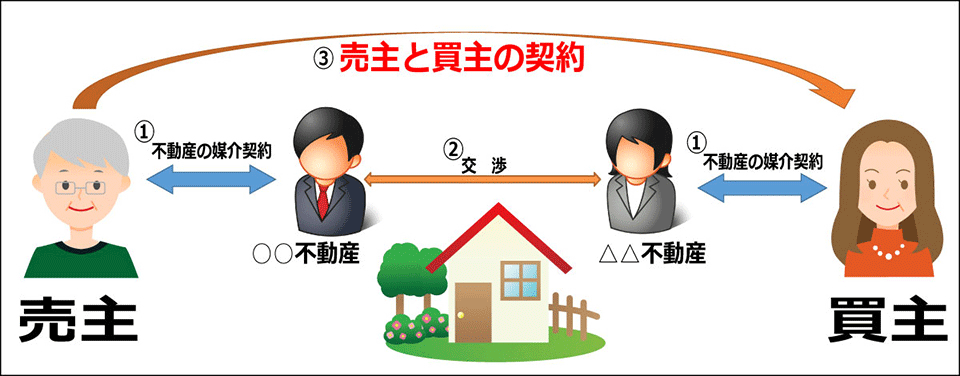
仲介の不動産業者はそれぞれのお客様のために、①物件の調査②価格の査定③広告④売買契約の作成⑤重要事項説明など、さまざまな業務をしてます。
そして、仲介の不動産業者に対し、不動産売買価格に応じて一定の仲介手数料が発生します。
<仲介手数料 2014年4月1日施行>
- 売買代金
(消費税を含まない) - 200万円以下の金額
- 200万円を超え
400万円以下の金額 - 400万円を超える金額
- 媒介報酬(仲介手数料)
(消費税を含む) - 5.4%以内の額
- 4.32%以内の額
- 3.24%以内の額
一般的に、3つに区分して計算するのは面倒ですので、不動産売買価格が400万円(税別)を超える場合は、次の簡易計算式が使われます。
仲介手数料(税抜)=売買価格の3%+6万円
例えば、2,000万円の不動産を売買した時は、
買主は2,000万円×3%+6万円=66万円(税抜)
売主も2,000万円×3%+6万円=66万円(税抜)
の合計132万円(税抜)の仲介手数料が必要となります。
取引の目途がたっていない場合は、売主買主を見つけたり、トラブル防止などのメリットがありますので、仲介手数料を支払う意味があります。
しかし、「親族間で売買」、「隣近所の人と売買」などで、既に売主買主が決まっており、トラブルも発生しにくい状況であれば、仲介手数料を支払ってまで不動産業者を通して取引をするメリットはあまりありません。
このような場合に、仲介業者を通さずに売主買主が直接取引することを「個人間売買」といいます。
個人間売買に適する取引
下記の2点に該当すれば個人間売買に適しているといえます。
- ①売主買主が決まっている
- ②不動産そのものについてトラブルがない
■仲介業者の主な業務
- ①権利関係の調査
- 登記簿謄本・公図・建物図面・地積測量図などで、不動産の権利関係を調査していきます。
- ②現地調査
- 現地で、付帯設備、生活関連施設(電気・ガス・水道)などを調査します。
- ③法令上の制限の調査
- 建物が建築できるかなどの調査を行います。
- ④価格の査定
- 適切な売買価格を査定します。
- ⑤取引の相手を見つける
- 売主側の業者はより高く買ってくれる人を、買主側の業者は要望に沿った売り物件を探します。
- ⑥売買契約書の作成
- 条件を交渉し、売買契約を作成します。
- ⑦重要事項説明(法的義務)
- 買主に対して、取引物件や取引条件等に関して説明します。
不動産は一般的に高額な取引のため、適切な取引の相手方を見つけることは難しく、⑤の「取引の相手方を見つける」は仲介業者に依頼する最大のメリットであるといえます。不動産業者を通したほうが良い場合は、信頼できる不動産業者をご紹介いたします。
取引価格について
不動産の取引価格を決定することは非常に重要なことです。
それではどのようなことに注意して決めればよいのでしょうか?
■不動産業者の査定方法
仲介業者に依頼した場合、取引価格は次のように決定されます。①売主が「売却希望価格」を伝える、②宅建業者が「査定価格」を価格査定マニュアルに基づいて算出、③売主と話し合いをして「売出価格」を決定④買主が「買主希望価格」を提示⑤売主・買主間で「最終価格」を合意。
ポイントは②の「査定価格」ですが、これは価格査定マニュアルや、同種の取引事例等を根拠として不動産業者は売主に意見します。
■公的価格について
時価以外の目安として活用されるのが公的価格となります。
公的価格には次の4つがあります。
| 種 別 | 価格 水準 ※ |
目 的 | 実施時期 |
|---|---|---|---|
| 公示価格 | 100 | 一般の土地取引の取引価格に指標(目安)を与える。 | 毎年1月1日を価格判定の基準日として、毎年3月下旬に官報にて公示。 |
| 基準値の標準価格 | 100 | 地価公示の補完的役割。 | 毎年7月1日を価格判定の基準日として、毎年9月末日に都道府県の公報にて公表。 |
| 路線価 | 80 | 相続税や贈与税の課税価格を評価するための基準となる。 | 毎年1月1日を価格判定の基準日として、毎年8月上旬に国税庁より公表。 |
| 固定資産税の評価額 | 70 | 固定資産税・登録免許税・不動産取得税等の課税標準となる。 | 3年ごとの基準年度に行われる。基準年度の1月1日に価格評価を行う。 |
- ※
これらの価格は、「総合土地政策推進要綱(平成3年1月閣議決定)」により、平成4年から運用されています。
■個人間取引における低額譲渡の判断基準について
個人から個人へ低額譲渡と税務署にみなされた場合、買手には時価と売買価格の差額に対して贈与税がかかります。これは相続税法7条に規定されています。
相続税法7条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合にはその規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。以下略
ここで言う「著しく低い価額の対価」につていは、ふたつの判決例があります。
<判決例1>(平15.6.19裁決、裁決事例集No.65 576頁)
「著しく低い価額の対価」に当たるとしてなされた原処分は違法であるとした裁決。
相続税法第7条にいう「著しく低い価額の対価」に該当するか否かは、当該財産の譲受けの事情、当該財産の譲受けの対価の額、当該財産の市場価額及び当該財産の相続税評価額などを総合勘案して社会通念に従い判断すべきものと解するのが相当である。(裁決判断より)
- →
この事例は、相続税評価額(路線価)を超える(約103%)価格で取引をした事例です。
<判決例2>(東京地裁平成19年8月23日判決)
「路線価での譲渡を著しく低い価格でない」とした判例
(以下長文ですが、判決の要旨です。)
- ①法7条にいう「著しく低い価額」の対価とは、その対価に経済合理性のないことが明らかな場合をいう。
- ②その判定は、個々の財産の譲渡ごとに、当該財産の種類、性質、その取引価額の決まり方、その取引の実情等を勘案して、社会通念に従い、時価と当該譲渡の対価との開差が著しい否かによって行う。
- ③この点について相続税評価額の扱いが問題になる。相続税評価額は、時価とおおむね一致すると考えられる地価公示価格の約80%とされている。そうすると相続税評価額を対価とする土地の譲渡は経済合理性にかなったものとはいい難い。しかしながら、一方で、80%という割合は、社会通念上、基準となるべき数値と比べて一般に著しく低い割合とはみられていない。また、課税当局が相続税評価額(路線価)を地価公示価格の80%を目途として定めている理由として1年の間の地価の変動の可能性が挙げられていることは、地価が1年の間に20%近く下落することがありうることを示すものである。そうすると、相続税評価額を基準として土地の譲渡の対価とすることが経済合理性のないことが明らかであるとまでは言えない。よって、相続税評価額を基準として土地の譲渡の対価として土地の譲渡が行われた場合に、原則として「著しく低い価額」の対価による譲渡ということはできない。
- ④法7条は、租税負担回避の意図・目的があったか否かを問わず、また、当事者に実質的な贈与の意思があったか否かをも問わずに適用がある。
- →
この事例は、路線価とほぼ同額で取引をした事例です。
上記裁決・判例のように、路線価で売買をした場合は、相続税法7条のいう「著しい低い価格」には該当しにくいとは思われますが、最終的には税務署が個々の具体的事案に基づき判定します。
- ※上記内容は個人→個人への売買となります。個人→法人、法人→個人、法人→法人の売買には該当しませんのでご注意下さい。
瑕疵担保責任について
「瑕疵」とは、法律用語で「目的物が通常有すべき性質や性能を有しないこと」を言います。そしてこの「瑕疵」について売主が責任を負うことを「瑕疵担保責任」と言います。
当初から売主・買主ともに「瑕疵」が分っていれば「瑕疵」を前提に取引をしますのであまり問題とならないのですが、買主が知らない瑕疵(隠れた「瑕疵」)があった場合に問題が発生します。
例)「現状のまま引き渡す」という条項がある中古住宅の売買で、買主が購入した後に雨漏りすることが発覚した場合に、売主に瑕疵担保責任が追及できるのか。
■民法上の瑕疵担保責任
民法上の瑕疵担保責任は、買主が瑕疵の存在を知ってから1年以内に行使しなければなりません(民法570条、566条3項)。この法律は強行規定でないため「瑕疵担保責任を負わない旨の特約」又は「瑕疵担保責任の期間を2か月にする」などの特約は可能です。ただし、売主が知っていながら買主に告知しなかった瑕疵については、売主は責任を負わなければなりません(民法572条)。
なお、買主の売主に対する瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、目的物の引渡後10年で時効により消滅します(最判13.11.27)。
■宅建業法上の特則
宅建業者が売主となり、宅建業者でないものが買主になる時は、民法上1年とされている瑕疵担保責任期間を、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、買主に不利となる特約をしてはならないと規定されています(宅建業法40条)。
例)不動産業者が売主となって中古住宅を販売するような場合に、「建物に対する瑕疵担保責任の免除」特約を付けて売買契約を交わしたとしても、無効となります。
■媒介業者の調査・説明責任
媒介業者は、売買の当事者でないので原則瑕疵担保責任を負いません。
しかし宅建業法35条では以下の規定をしています。
宅建業者が不動産売買の媒介・代理を行う場合の売買当事者等に対して、取引主任者によって、法所定の重要事項を説明しなければならない。(業法35条要約)
この規定は、不動産取引のプロである取引主任者が、売買当事者に対して取引物件・取引条件などの重要事項を説明することにより、契約締結後の紛争を防止するためのものです。
特に買主にとっては、取引物件に関し正確な情報を持ち合わせていないため、重要事項説明の役割は大きいと言えます。
■主な重要事項説明項目
- ①物件に関する権利関係の明示
- 登記された権利の種類、内容等
- ②物件に関する権利制限内容の明示
- 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要等
- ③物件の属性の明示
- 生活関連設備の状況・耐震診断の内容等
- ④取引条件(契約上の権利義務関係)の明示
- 代金、交換差金以外に授受される金額及び目的・契約の解除に関する事項等
- ⑤取引に当たって宅地建物取引業者が講じる措置
- 支払金又は預り金の保全措置の概要・金銭の貸借のあっせん等
- ⑥区分所有建物(分譲マンション等)の場合
- 敷地に関する権利の種類及び内容・共有部分に関する規約等の定め等
上記が主な重要事項説明の項目です。
もしこれらの項目の中で故意に事実を告げない、不実のことを告げる等の行為があれば、媒介業者の調査・説明責任の問題となり、宅建業法違反の可能性もあります。
■主な宅建業者の責任
指示処分(業法65条1項・3項)、又は1年以内の業務の全部又は一部停止の処分(65条2項2号・4項2号)がなされ、さらに情状が特に重いときは免許の取消処分(66条1項9号)
ただ、不動産業者が隠れたる瑕疵を全て把握することは困難です。そこで売主等から「告知書」(所有者にしか分らない不動産の情報が記載されたもの)を提出してもらい、瑕疵について確認する事もあります。
よくあるご質問
- 県外に不動産があるのですが、手続きできますか?
- 当事務所は、オンライン申請に対応しておりますので、県外でも手続き可能です。追加報酬は発生しません。郵便代実費のみいただきます。
ただし、原則当事者の面談が必要となります。 - 質問に戻る
- 最初の相談の際には、何を準備すればよいですか?
- 下記の書類のうち、お手元にあるものをご準備下さい。
- 固定資産税の通知書、明細書(毎年4~6月頃に役所から届きます)
- 権利証
- 質問に戻る
- 不動産を売却して利益が出ました。税金の手続は必要ですか?
- 不動産を売却等をして得られた利益を譲渡所得といいます。個人が不動産譲渡所得を得た場合、その所得とその他の所得(給与・年金等)を分離して所得税と住民税が課税されます。
この譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間となります。
なお、住民税にも影響があることから、国民健康保険(会社員や公務員とその扶養者以外が加入する保険)料及び患者負担割合にも影響があります。社会保険加入者(健康保険・協会けんぽ)の保険料には、影響がございません。
※居住用財産の特例等で譲渡所得税が発生しない場合であっても、国民健康保険料は増加する可能性がございます。なお、扶養家族に不動産譲渡所得が発生した場合、扶養控除から外れる可能性があります。 - 質問に戻る
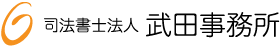
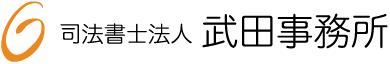
 メニュー
メニュー